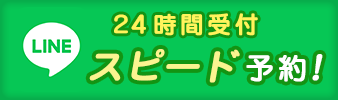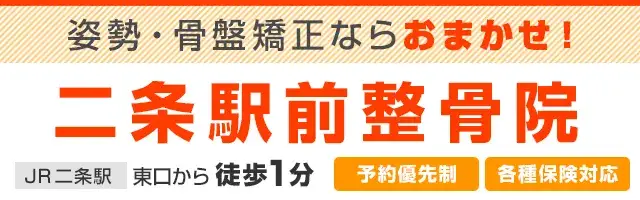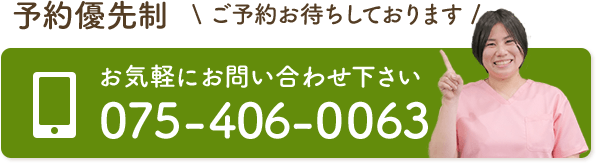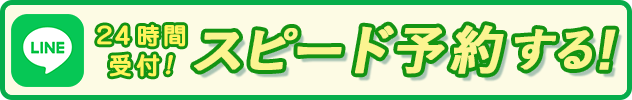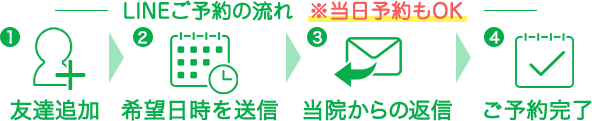巻き肩

こんなお悩みはありませんか?

長時間のデスクワークやスマートフォンの使用で前かがみの姿勢が続いている
胸部の筋肉が縮まり、肩甲骨が前に引っ張られていると感じる
上半身の筋肉のバランスが崩れている気がする
スマートフォン操作時に首が下を向き、肩が丸まってしまう
横向きで寝る習慣があり、肩に体重がかかっている
眼精疲労や頭痛に悩まされている
巻き肩について知っておくべきこと

身体の前面の筋肉が縮こまってしまうと、呼吸がしづらくなります。肋骨の動きも制限されるため、呼吸が浅くなり、体内に取り込める酸素量が低下します。これによって血液中の酸素量も減少し、血流が悪化する可能性があります。呼吸が浅くなると、疲労感や眼精疲労、頭痛、睡眠の質の低下、代謝の低下など、さまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、首から肩、上半身の筋肉が縮んだままになることで、柔軟性を失います。その結果、血流が悪くなり、肩こりや首こりの原因となります。
また、巻き肩を軽減しようと無理に背筋を伸ばすと、腰が反った状態になりがちです。いわゆる反り腰の状態となり、背骨本来のS字カーブが崩れて腰に負担がかかり、腰痛につながるおそれがあります。
症状の現れ方は?

スマートフォンを見ているとき、肩が丸まり、頭が前に出た姿勢になりやすいです。この姿勢が定着すると、見た目にもマイナスな印象を与える可能性があります。
また、スマートフォンを長時間見る習慣がある方は、身体を動かす機会も少なくなっているかもしれません。運動量が減ることで筋力が低下し、正しい姿勢を保つことが難しくなるという悪循環に陥るおそれがあります。
肩甲骨が動かない状態になると、肩や背中だけでなく、首や腕にも負担がかかりやすくなります。その結果、首や腕に負担がかかり、五十肩や腕のしびれなど、深刻な症状に発展する可能性もあります。
さらに、筋肉の緊張が続くと血流が悪化し、痛みやしびれ、冷え性や頭痛などの症状があらわれる可能性も高まります。
その他の原因は?

巻き肩とは、主に胸の奥にある筋肉がこり固まり、肩が前方に突出した不良姿勢の状態を指します。長時間のスマートフォン操作やデスクワーク、横向きの睡眠姿勢などによって引き起こされ、首こりや肩こり、姿勢不良、呼吸機能の低下などを誘発するおそれがあるため、適切に対処することが大切です。
長時間のスマートフォン操作やデスクワークによる負担で、肩が前方に突出し、前傾姿勢となってしまうことがあります。画面をのぞき込む姿勢や、画面と視線の高さが合っていないこと、肩に力が入った状態、両手の手のひらを長時間下に向ける作業などが原因となり、巻き肩のリスクが高まります。
巻き肩を放置するとどうなる?

血行不良を引き起こし、慢性的な肩こりや首こりにつながり、日常生活に支障をきたす可能性があります。首や肩まわりに負担がかかることで、筋肉がこりやすくなり、その結果、慢性的な肩こりに悩まされることがあります。また、身体の柔軟性が低下します。
その状態を放置すると、腕が肩の上にあがらなくなる、いわゆる四十肩や五十肩の状態になる可能性があります。これは短期間で発症するものではなく、長い時間、同じ姿勢をとり続けることで、次第に巻き肩が進行していきます。背中が丸く見えるだけでなく、姿勢が悪くなり、血流の流れも悪くなる可能性が高まります。
当院の施術方法について

当院の施術方法では、まず初めに肩まわりの筋肉を緩める施術を行い肩甲骨はがしや矯正施術など、さまざまな施術をご用意しています。肩甲骨はがし、矯正の施術は、いずれも一度の施術では十分な効果が得られにくい可能性があります。そのため、継続的に施術を受けていただくことが、より効果的であると考えられます。
軽減していく上でのポイント

筋肉のバランスを整えるためには、特定のエクササイズが効果が期待できます。主に胸部の筋肉を伸ばすストレッチや、背中の筋肉を強化する筋力トレーニングが推奨されています。例えば、壁やドアフレームを利用した胸部のストレッチや、バンドを使った肩甲骨を引き寄せる動作は、肩の内旋を軽減し、胸郭を開くのに役立ちます。
また、寝る姿勢については、仰向けで寝ることをおすすめします。横向きに寝ると肩が前側に出やすくなるため、天井を向いた姿勢で寝ることで、自然と肩が本来の位置に戻りやすくなります。
日々の生活習慣における小さな工夫が、巻き肩の軽減にとって非常に有効です。特に姿勢を意識することが重要であり、正しい姿勢を保つためには、デスクや椅子の高さを調整して作業環境を最適化し、長時間同じ姿勢で過ごさないよう心がけることが大切です。
監修

二条駅前整骨院 院長
資格:柔道整復師